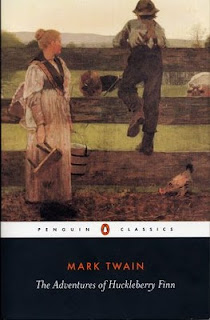 |
| The Adventures of Huckleberry Finn |
Mark TwainのThe Adventures of Huckleberry Finnについて議論するにあたり、まずはテクストがテクストそれ自体について述べている箇所を冒頭より引用したい。
You don't know about me, without you have read a book by the name of The Adventures of Tom Sawyer, but that ain't no matter. That book was made by Mr Mark Twain, and he told the truth, mainly. There was things which he stretched, but mainly he told the truth. That is nothing. (49)この書き出しが注目に値するのは、ひとつには「語られていることが必ずしも実際に起きた出来事と一致するわけではない」と、テクストの虚構性がほのめかされているためであり、もうひとつにはあたかも自身が想像上のキャラクターに過ぎないことを認知しているように、語り手Huckが先行するテクストや作者Twainについて言及しているためである。これまでHuckleberry Finnは「見たままの情景を無教育な少年の借りものでない俗語・方言で直接、感覚的に描写しており、その結果Mississippi河の夜明けは彼以外の描写では表現できぬ具体性と特殊性を持って読者に迫ってくる(『総説アメリカ文学史』, 159)」と評され、リアリズムの側面が強調されて読まれてきたように思える。しかし、その一方で、一貫した真実性を持った語りを否定するのに十分な矛盾がテクストに盛り込まれていることもまた事実である。そのため、この作品における個々の情景描写が持ちうる意味を考える際にもテクスト全体のコンテクストと照らし合わせてみる必要があるはずだ。本稿では、Huckleberry Finnの形式と内容のそれぞれを作品の持つ虚構性に焦点を当てることによって再検討し、リアリティを自明視する限りにおいては十分に議論されえない問題点を明らかにしていきたい。
アメリカ文学に限らず、テクストが成立した過程をテクスト自体が説明することは多くの冒険譚に見られるパターンである。冒険譚が地理的ないし歴史的に隔たった経験を読者に報告する体裁をとる以上、信じられないような話に信憑性を持たせるための手続きが欠かせないことは納得のできることだ。ここで目を引くのは、マルコ・ポーロの『東方見聞録』1 をはじめ、ほとんどの冒険譚がその真実性を真っ向から主張している2 のに対して、Huckleberry Finnは真実と虚構が入り混じっていることをある程度認めることによって、逆に真実らしさを獲得しようとしていることである。歴史的事実を普遍的なものとして記述することが原理的に不可能であるという認識が前提となっている現代においては、むしろ後者のほうが信憑性の高いようにさえ思える。
ただし、Huckは具体的にどの部分が誇張であったかについては「どうでもいいことだ」とはぐらかしてしまう。彼が曖昧なままにしているもうひとつのことはHuckとTwainの関係である。作品の末尾からHuckがこの本を世に送り出すのに大変な苦労をしたらしいことはわかるが、それでは具体的にどのように貢献したのかということについてははっきりとしない。
[S]o there ain't nothing more to write about, and I am rotten glad of it, because if I'd a knowned that a trouble it was to make a book wouldn't a tackled it and ain't agoing to no more. (369)ここでは"write"という言葉が用いられている。しかし、Huckがペンを取って何百枚もの原稿と向き合っている姿は想像しにくい。まずは、彼の語りがしばしば現在形で書かれていることが理由として挙げられる。確かに短い手紙やメモを書く場面はいくつか見られるが、そのおぼつかなさはむしろ日常的に記録を残している可能性を否定する根拠に数えられるものだ。また、11章でJudith Loftusとのやりとりに必死になるあまり、自分であらかじめ用意していた偽名を忘れてしまったことを思い起こすと、彼は自らの体験を正確に回想することには向かなさそうな語り手である。また、標準とされている英語に照らしたとき、Huckの言葉は文法や綴りの間違いにあふれている。例えば、"[Widow Douglas] would sivilize me (49)"という箇所では、civilizeとすべきところがsivilize と間違えられることによって、いかにHuckが文明化されていないかが露呈している。最後に、語り手のリアリティを決定的に否定するのは、Huckが語り手とされているのにもかかわらず、彼自身には出来上がったテクストを読み返すことが出来そうにないことである。別の言い方をするならば、この作品はHuckが読むために書かれたものではないのだ。このように考えるとHuckのHuckleberry Finnに対する貢献は、作者の想像力の中で動き回ったのみであるという、至極当たり前の結論に達せざるを得ない。しかし、当然のことのようではあるが、ひとたびこのことを認めてしまえば、Huckが「自然で無垢」どころか極めて人為的に創られたキャラクターであることも認めることになる。つまり、Huckleberry Finnのリアリティを保障しているものは、実は冒頭から末尾まで繰り返されている境界のはっきりとしない作者Twainと語り手Huckが同時に存在しているというメタフィクション的仕掛け、すなわちテクストの虚構性なのである。
通常ならば語るはずのない、また仮に語ったとしてもまともに聴きいれられることのない語り手が語るためには、作者が干渉し、語り手に代わって語りを捏造することが欠かせない。ことの善悪はさておき、ここからはこの捏造――作者の想像力の働きと言い換えることもできるだろう――が作品にもたらす意味を考察したい。まずは先ほど挙げたsivilizeという綴りの間違えを改めて見てみよう。ここで発音が同一であるcとsが混同されるためには、Huck自身がそれを頭のなかで思い描いたり口に出したりするのではなく、実際に書き間違えてみせなければならないはずだ。しかし、前述の通りそのようなことはありえないので、作者の捏造と言わざるをえない。同様のことは黒人奴隷のJimについても言える。そもそもアルファベットの読み書きができず、フランス人が自分たちと違う言葉を話しているということさえ理解するのに苦しんだJimには、Huckleberry Finnで用いられているような、標準とされる英語よりも音声に近づけた独特の表記法に基づく別の言語を話しているという自覚はないはずだ。ちょうど日本が「チパング島」として中世ヨーロッパに紹介されたように、HuckとJimは作者によって、標準とされているものとは異なる別の記号体系を無自覚のうちに押しつけられているのである。
HuckがHuckleberry Finnの読者として想定されていないことは先に述べた通りだが、逆に想定されている読者にとっては、"[C]ould say the multiplication table up to six times seven is thirty-five (65)"が明らかな間違いだということはすぐにわかるはずだ。また、Huckが"Polly-voo-franzy (135)"と言ったのが、本当は"Parlez-vous fran?ais?"のことを言いたかったのだということもわかる。さらに、22章でHuckはサーカスの団長が団員によって本当に騙されたのだと信じこみ、あらかじめ計画された演出であったことを疑おうともしないが、それが勘違いであることは想定された読者にとっては明白なはずである。そして、標準とされている英語やシェイクスピアの諸作品、そしていくつかの歴史的事件についての知識を持っていることも、想定されている読者たる条件であるらしい。こうして作品の随所に散りばめられた「ユーモア」の数々を振り返ると、その多くが作者の意識によって捏造されたHuckやJimの無意識が犯す過ちを、想定されている読者が「発見」することによって成立するものであることが明らかになる。そのため、想定されている読者はHuck本人よりもHuckをとりまく状況を把握しているような錯覚に囚われかねないが、それが錯覚であることは改めて強調しておかなければならない。『見聞録』では、「チパング島」における当時の仏教信仰について「実に悪魔的で、とても紹介することができない(『見聞録』, 208)」としている。自らの立ち位置から排除すべきイメージを他者に投影するライティング――Huckleberry FinnにおいてはHuckやJimの語りを一方的に文字化すること――は、彼らを想定されている読者とは異質の存在として区別するだけでなく、「未開」または「発展途上」というイメージを付加し、架空の上下関係を築くことを意味している。想定されている読者には全く理解することのできないテクストを作品の一部に挿入することや、活字による表記を離れることもできたかもしれないが、Huckleberry Finnにはそのような試みは見られない。
さて、作品がこのような階層構造を保持していることは事実であるが、それだけを根拠にTwainのライティングを差別的なものとして批判することはできない。また、Twainが人種問題についてどのような立場をとっていたかを詮索することもテクストを分析する鍵とはならない。ここで重要なことは、Huckleberry Finnが抑圧されている者の語りを代行することが原理的に不可能であり、それがあたかも可能なことであるかのように振舞うことがどれほど滑稽であるかを示すエピソードの集積によって成り立っているという内容的な特徴に目を向けることである。例えば、Huckは言い逃れをするために実にいきいきと架空の家族や架空の死者を捏造している。また、つい先ほど口にしたことについても、そのままでは辻褄があわず都合が悪いことに気がつけばすぐに新たな意味づけを行なっている。これらはまさしく、現在による過去の抑圧として説明することができる。他者の無意識を捏造しようとする行為のなかで特に過激なものは、実際にあったことを夢だと説き伏せ、言ったことを言わなかったと主張することである。15章で自分が騙されたときには怒りを露わにしたJimだったが、34章では何食わぬ顔でTomやHuckに話を合わせている。そして、語りの代行がどれほど不毛であるかを最も顕著に表しているのが、アルファベットを綴ることのできないJimに無理やり筆記具を持たせ、Tomの用意したお手本をもとに大きな砥石に文言を刻みつけさせることにより、語る内容だけでなく語り手をも捏造してしまった38章のエピソードである。このように、Huckは作者Twainによって抑圧されている一方で、語り手という特権的な立場にある以上、Jimをはじめとした他のキャラクターを抑圧する側でもあるのである。
38章ほど直接的ではないにせよ、やはり指摘しておかなければならないのが生前、死亡記事や怪我や病気で苦しんでいる者たちの記事を蒐集し、死者を哀悼する詩を詠んでいたとされるEmmeline Grangerfordという少女である(17章)。Emmelineはその善行のために人々から大いに感謝されていたようだが、彼女の想像力の源泉は在りし日の故人との思い出よりも、死という現象そのものだったと考えられる。つまり、彼女が詩を通して語ったことは、不幸に遭った者たちの実態とは乖離したものである可能性が高いが、殊に故人ともなれば、例え見当違いなことが詠まれたとしても本人が異論を唱えるようなことはありえない。死者についてばかり語った少女の不気味さをつきつめていくと、このように一方的な意味づけを繰り返していたことに集約するのではないだろうか。皮肉にもそのEmmelineはHuckがGrangerford家に迎えられたときにはすでに帰らぬ人となっており、神聖化され、家族から無条件の愛情を注がれる対象となっている。
Emmeline以外にもHuckの父親、Grangerford家の男性たち、Boggs、そして遺言によってJimを解放したOld Miss Watsonなど、登場人物がつぎつぎに他界してゆく。そればかりか、死は慣用表現としても作品中に頻出する。最も多いのが"I most wished I was dead (51)"や"I would die first (254)"など、「死んだほうがましだ」という用法である。次に、 "perfectly dead and still (191)"や"like everybody's dead and gone (288)"という形で静寂を表す箇所も少なくない。また、頻度は下がるが、"The people most killed themselves laughing (214)"と"Jim was pleased most to death (368)"では、死という意味を離れた強調表現として使われている。Huckはなぜ死について執拗に語るのだろうか。また、語り手本人の台詞はなぜこれほど限られているのだろうか。思えばThe Adventures of Huckleberry Finnと銘打たれていながら、作品中でHuckのとる行動は原則的に逃亡であり、事件が起きたときにも積極的に危険を冒すよりは傍観者であり続けることが多い。いつでも逃げられるようにいかだを隠していたのと同じように、Huckはどのようにでも語ることのできる死者をはじめとした被抑圧者については雄弁に、逆に自らについては曖昧に語ったと考えることもできる。
このように、Huckleberry Finnは従来言われてきたように文体や方言の表記法に関する実験的な試みであると同時に、それが生み出すとされるリアリティが本質的には虚構に過ぎないことを絶えず確認するように書かれている。そして、ひとたびこの虚構性を認めれば、「牧歌的なユーモア」とされてきたものは「無知を装ったアイロニー」となり、作品のタイトルと内容の不一致も浮き彫りになる。ついには作品を「Huckの冒険」として読むことができなくなる。Huckleberry Finnが優れた作品であるならば、それは「無垢で純真な少年Huck」が「南部の典型的な姿」を「独自の言葉」で語ったためではなく、むしろそのいずれについても不可能であることを背理法的な手続きによって証明しているためである。
註
1 『東方見聞録』の著者はマルコ・ポーロとされることが多いが、厳密には1298年にマルコがジェノアで投獄されたときに同じ獄舎にいたピサの出身者、ルスティケロが書き上げたものだ。捕らえられたマルコはヴェニスの父のもとに手紙を出し、26年に及んだ冒険のあいだに書きためたノートを送らせた。ルスティケロはマルコの口述よりもこのノートを基礎に自らの文体に則して旅行記をまとめたので、最初の原本はイタリア語がかった中期フランス語で書かれたとされている。マルコとルスティケロという2人の媒介者がテクストに関わっているという点で、『見聞録』とHuckleberry Finnはよく似ている。また、当時はまだ印刷技術が発明されていなかったため、ルスティケロの原書を書き写すときにマルコ本人から直接聞いたことなどを付け加えた人もあったと考えられ、古写本、古版本は合わせて140種類以上あると言われている。(『見聞録』, 解説)
2 「これはヴェニスの賢明で気高い市民マルコ・ポーロ氏によってのべられたもので、彼はその眼でこれらを見たのである。中には彼の親しく接しなかったものもあるにはあるが、それも信用ある人から聞いたものである。しかし見たことと聞いたことははっきりと区別してある。本書を、真実をかたる信頼すべき書とするためである。(『見聞録』序文, 10)」序文にはこのようにあるが、本文における経験と伝聞の区別は曖昧であり、そのため『見聞録』には神話に基づく荒唐無稽なエピソードが多い(もっとも、13世紀の史料としては驚異的に正確であるという見方が歴史家の間では支配的なようだ)。
参考文献
Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn (London: Penguin Books Ltd.) 1985.
マルコ・ポーロ 著, 青木富太郎 訳『世界探検全集1東方見聞録』(東京: 河出書房新社) 1998.
大橋健三郎, 斎藤光, 大橋吉之輔 編『総説アメリカ文学史』(東京: 研究社) 1975.
| The Adventures of Huckleberry Finn (Penguin Classics S.) Mark Twain Peter Coveney |
| 総説アメリカ文学史 大橋 健三郎 |

